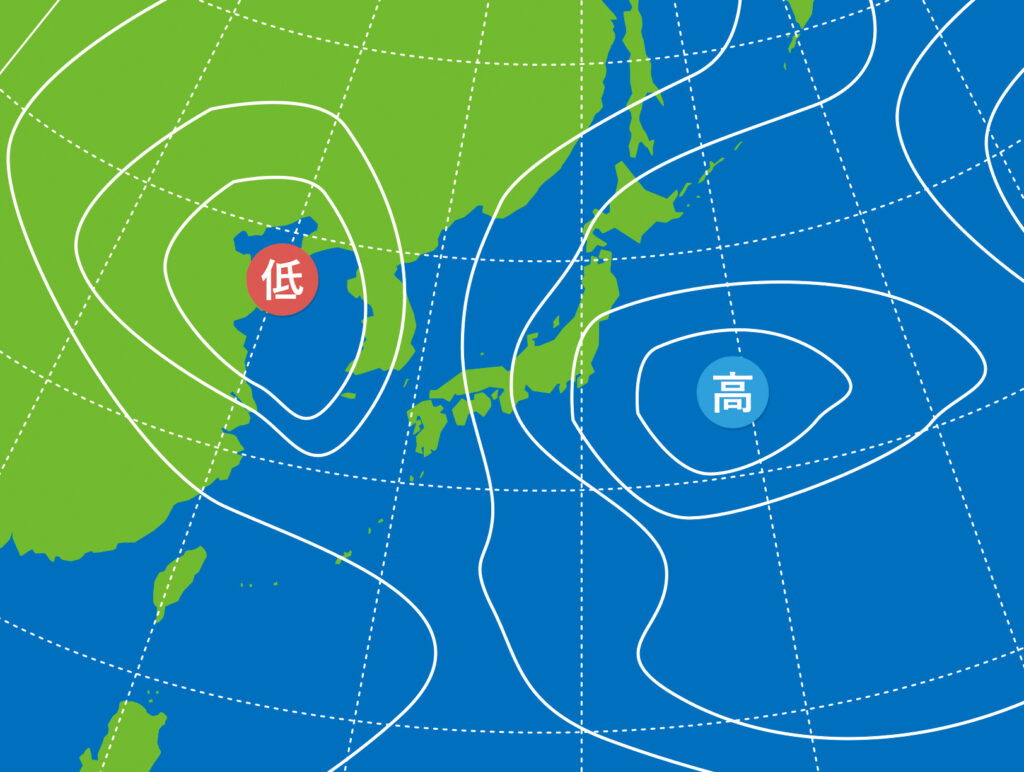
前回のブロブ “highly sought-after:seekはそのまま、でもhighlyは気を付けて” では、
人気怪談師のプロフィールを読みました。
記事ではその後、怪談の歴史に話が移ります。
平安時代の書物に既に怪談話があり、日本は長い怪談の歴史があるそうです。
The Japan News・“Ghost Story Boom Triggered by Social Conditions; Experts Theorize Why People Are Drawn to Ghost Stories”
そんな怪談の変遷に、一つ発見がありました。
時は流れ、1990年代
“real-life ghost stories” based on personal experiences emerged and went mainstream.
「個人の経験に基づく実生活の中の怪談が生まれ、そして主流になった」
随分前になりますが、“go public 悪いことではないけれど” の回で、
“go 補語~”で、「~になる」というのを勉強しました。
補語にはネガティブなものが来ることが多いですが、決して悪い事ばかりじゃない。
今回の”go main stream”もまさにそれ!
ポジティブな新たな用例に出会えました。
記事に戻ると、
1990年代のそうした流れは、バブル経済崩壊の社会の不安定さと関連しているそうで、
続く専門家のお話に今日の勉強がありました。
“Ghost stories depict a mysterious and unstable world,” Yoshida said. “That’s why they resonate with unstable social climates and easily attract people.”
social climates 「社会の気候」?
話の流れからして”地球温暖化”とか関係なさそうですし...
調べますね。
social climate「社会情勢」
「気象、天気」に関するある地域の「傾向」が”climate”
そこから、その土地・社会・時代の「傾向、風潮」も表す様になったようです。
例えば、
the cultual climate of the reagion
「その地方の文化的風潮」
では、今日の文の訳
「怪談はミステリアスで不安定な世界を描く、だから不安定な社会情勢と共鳴し簡単に人を引き付ける」
現代社会の閉塞感、見通しが立たない将来
怪談が流行る下地はある訳なんですね。
なるほど、深い。
季節的にはまだまだ怪談シーズン
動画もいっぱい有りそうですし
今晩あたりいかがです?
そのあなたの後ろにいる人と。
今日もお付き合いいただきありがとうございました。
See you tomorrow.
